処暑
処暑は暑さが止まるころという時期。恵那山麓では川の水がぐっと冷たくなります。「夏の終わり」と「秋の始まり」が交錯する時期です。お盆を過ぎ、夏休みの終わりが見えてくる頃です。
岩村城下町で出会う、二百年前の思想
岩村城下町で出会う、二百年前の思想
今年の夏、私は岩村城下町へと何度も足を運びました。坂道を上り下りするたび、目に入るのは佐藤一斎の『言志四録』の彫板。その言葉に心惹かれ、NPO法人いわむら一斎塾の鈴木隆一さんを訪ねました。鈴木さんの話から、佐藤一斎と岩村藩の深い結びつきを知ります。一斎は、岩村藩が江戸に構えていた屋敷の一つ、下屋敷で生まれました。江戸時代、美濃国初の藩校「知新館」を創設し、「文教の藩」として教育に力を注いだ岩村。その精神は、恵那市に今も息づく「市民三学」の教えへと繋がっています。
三学の精神(佐藤一斎『言志晩録』より)
少にして学べば、則ち壮にして為す有り
壮にして学べば、則ち老いて衰えず
老いて学べば、則ち死して朽ちず
「人は一生を通じて学び続けることで、社会に貢献し、精神は朽ちることなく生き続ける。」二百年前のこの思想が、情報過多の現代にこそ、私たちの生き方を見つめ直すきっかけを与えてくれるのかもしれません。佐藤一斎の生きた時代には、岩村城はまだその姿を保っていました。岩村城跡で石垣に手を添えると、時代を超えた対話が生まれるような気がします。
十月には「佐藤一斎學びのひろば」がグランドオープンを迎えます。なぜ「学」ではなく、あえて旧字体の「學」を選んだのでしょうか。「學」は、子どもが建物の中で立派な大人になるように教えを受ける姿を描いた象形文字に由来するそうです。人と人が交わる中で知識が育まれる、その営みを象徴していると鈴木さんは言います。学びとは、単なる知識の習得ではなく、人との関係性の中で育まれるものなのだと改めて教わります。
提灯が外され、夜がぐっと長くなったように感じる岩村城下町。今度は一泊して、じっくりと『言志四録』に触れてみたいと思いました。
Shosho – Where Summer and Autumn Meet
Shosho – Where Summer and Autumn Meet
Shosho marks the moment when summer heat begins to fade. In the foothills of Mt. Ena, the river
runs cooler, dragonflies flit above ripening rice, and the air hints at autumn’s approach.
Iwamura – A Castle Town of Wisdom
In the historic castle town of Iwamura, wooden plaques engraved with the words of Edo-period
scholar Sato Issai line the slopes. Born here, Issai founded Chishinkan, Mino’s first domain
school—Mino being the historic province that now forms the southern part of Gifu Prefecture—, and
inspired the “Three Principles of Learning”—a timeless call to pursue knowledge (学) throughout
life.
This October, the “Sato Issai Manabi no Hiroba” will open, its name written with the traditional 學,
an ancient pictograph of a child learning beneath a tree. It reflects the idea that learning is nurtured
through human connection, not simply acquired from books.
As you wander the quiet streets or touch the stone walls of Iwamura Castle’s ruins, you may feel the
presence of centuries past—and an invitation to weave your own story into this living history.
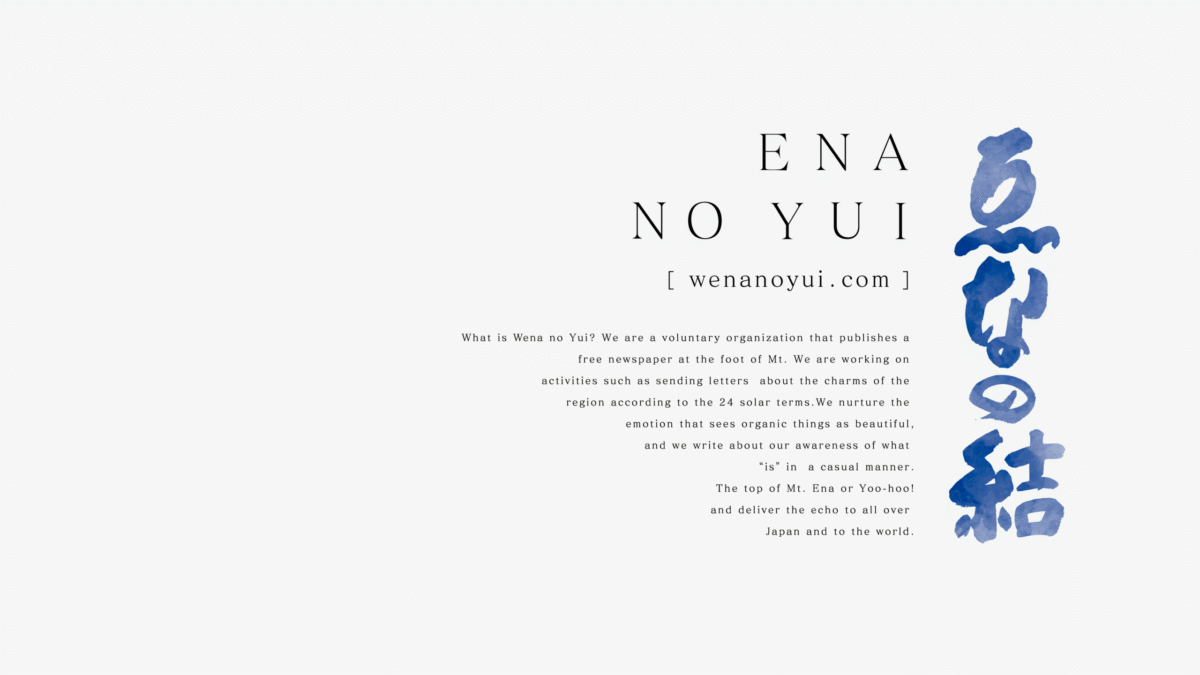



コメント